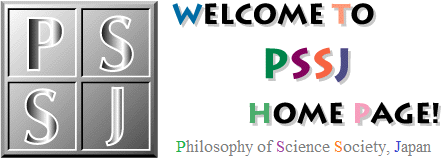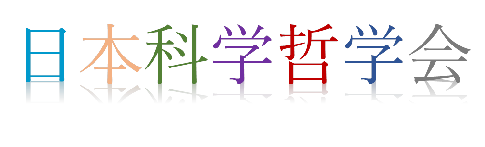年次大会 > 第58回(2025年度)大会 サテライトイベントのご案内
日本科学哲学会第58回(2025年度)大会
サテライトイベントのご案内
日本科学哲学会第58回大会のサテライトイベントとして、以下の催し物がございます。
ご都合のつく方は、ぜひ参加ください。
- 日時:2025年11月28日(金)18:00~20:00
- 会場:中央大学(多摩キャンパス) FOREST GATEWAY CHUO F504教室(フォレストゲートウェイ建物5階)およびZoomウェビナー
- サテライトイベント
現代において正義をいかに語ることができるか――感情と理性と公共性をめぐって
- オーガナイザ:久木田水生
- 提題者:朱喜哲、ベンジャミン・クリッツァー
-
企画趣旨:
現在、私たちは分断された社会の中に生きていると言われる。20世紀半ば以降の大きなイデオロギーや社会的価値の喪失は、異なる文明圏の間の対立を露わにした。さらに近年ではジェンダーや性的指向、民族性や文化などのアイデンティティに基づく軋轢も顕著である。科学やテクノロジーに対する態度によってさえも人々は激しく対立している。このような分断の中では「何が正しいことか」についての判断はそれぞれのコミュニティの重視する価値によって異なっており、一つの「正義」を主張することはしばしば他のコミュニティの「正義」との衝突を招く。そしてそのことはさらに分断を深める結果に終わる。このような状況において、私たちはなお意味のある形で正義を語ることができるだろうか。それが可能だとすれば、それはどのようにしてだろうか。本サテライトイベントでは、正義にまつわる現代の困難な状況に抗して、公共的な正義について考察し提言をしてきた二人の論者、朱喜哲氏とベンジャミン・クリッツァー氏を招いて、この問題について議論したい。
-
日時
2025年11月28日18時~20時 -
場所
中央大学(多摩キャンパス) FOREST GATEWAY CHUO F504教室(フォレストゲートウェイ建物5階)およびZoomウェビナー
※多摩モノレールの「中央大学・明星大学」駅から中央大学に入り、すぐ見えるスターバックスの裏にある建物となります。
※ウェビナーの参加登録は下記からお願いします。https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m2qZ_X_oSz6SqkKlGjojmw
※機材も人手も乏しいので、ウェビナーについての不手際についてはご容赦ください。
-
講演者とタイトル、要旨
-
朱喜哲:「バザールの正義」と「クラブの善」:ローティ=ロールズの現代的可能性と限界
拙著『〈公正〉を乗りこなす』(2023年)では、ジョン・ロールズの正義論から「正と善の区別」をもっとも重要な教説として再構成し、リチャード・ローティの政治哲学、あるいはロールズ解釈と接木することで、その現代的な可能性を模索した。
その際の枢要な戦略は、ローティ政治哲学の重要な特徴である「公共的/私的」の区別と「正義/善」の区別を重ね、さらにそれをローティ由来の「バザール/クラブ」というともに商業的なメタファーから検討することにあった。
この説明戦略は、今日のように資本主義がデファクトスタンダードとして世界を覆い、かつ国家をはるかに超える規模で市民たちのプライバシーデータを管理・運用する大手プラットフォーマーを筆頭とした私企業が「公共」の担い手となる時代における「正義論」のアップデートという意義がある。
しかし、同時にこの図式においては不可視化しがちなのが市場の「外」、ハンナ・アーレントであれば「アゴラ(広場)」として位置づける伝統的な「公共」圏の存在とその責任である。
本発表では、2025年現在の「ことば」の環境を考える際に避けては通れないSNS時代の「言語=政治哲学」としてローティおよびロバート・ブランダムの議論を参照し、あらためて商業的モチーフから「公共と私」「正義と善」を捉えることの可能性とその限界を検討する。 -
ベンジャミン・クリッツァー:2025年における「公共的理性」の意義とその限界
2024年刊行の拙著『モヤモヤする正義』では、政治や政策の関わる問題について、属性や立場の違いからそれぞれに異なる利害を持つ人々が、自分の意見について互いに理由を提示して正当化しながら相手側の意見にも耳を傾けることで妥協や融和、相互承認を図っていく営みを「公共的理性」と表現した。また、同著ではJ・S・ミルの『自由論』を参照しながら「思想と言論の自由」を擁護しつつ、いわゆる「理性的な議論」の重要性を説いている。
一方、同著が出版された直後にアメリカではドナルド・トランプが大統領選挙に勝利して再選が決まり、現在、これまでになくバックラッシュが強まっている。また、日本でも直近の1~2年で排外主義やトランスジェンダーに対する差別はそれまで以上に急速に強まっており、その影響は選挙結果や入管政策などを通じて目に見える形で表れている。
この現状は、一面では、「理性的な議論」の必要性をさらに強めるものと言える。最近になって生じた排外主義やトランスジェンダーに対する差別の大半は、SNSやメディアによる虚構や誇張によって煽られた脅威・恐怖・不安感などの「感情」に起因するものであるからだ。
しかし、他方で、ミルが『自由論』で擁護したような「思想と言論の自由」が、外国人・性的少数者や女性に対するヘイトスピーチや侮辱的な言論を擁護するために利用されている事実を否定することもできない。手放しで「理性的な議論」を肯定することは、現状を放置したり悪化への加担につながりかねない。
今回は、2025年現在の状況をふまえつつ、改めて「公共的理性」の意義を考え直したい。
-
朱喜哲:「バザールの正義」と「クラブの善」:ローティ=ロールズの現代的可能性と限界
-
助成
このイベントは科研費基盤B、課題番号24K00001(代表:蔵田伸雄)の助成を受けています。 -
問い合わせ先
久木田水生 minao.kukita@gmail.com